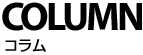
| ≪ 戻る | 目次 | 次へ ≫ |

楮製紙製マネキン/1950年代:村井次郎作
敗戦直後の窮乏状態にあって、衣をまとうことが、人間的尊厳を保つ重要問題であったことは、衣服を着せて見せ、販売するマネキンの必要がいち早く叫ばれたことで頷ける。
それは同時に、衣服をマネキンに着せることによって、より魅力的に服を見せ、厳しい世相にあって、何がしかの夢を提供する意味が込められていたと推察する。
この当時のマネキンの素材は、戦前島津マネキンが開発した和紙を主素材とした楮(ちょ)製紙製で、ものづくりにおける厳しい姿勢は戦後にも引き継がれた。
一旦、作り手の手から離れると、社会の荒波に晒される、辛く悲しい運命が待ち受けているマネキンに対して、せめて思いを込めて作りたいと職人は願った。この精神は、素材が1950年代終わりに、プラスチックになった以降も、基本的に変わることはない。
マネキンもまた、他の人形同様に、その姿かたちが「ひとがた」であり、100%人の手仕事から生まれることから、作り手の思いは色濃く投影されるのである。
戦後まもなく、全国に洋裁学校が急増し、家庭用ミシンが急速に普及した。このことは、特に日本女性の衣服の、和装から洋装への劇的な転換を意味していた。街中にはオーダーメード服の仕立てを生業にする洋装店が目立つようになった。このような店のショーウインドには1〜2体のマネキンが置かれ、目新しい衣服を身に着けて、厳しい時代を生きる人々に夢を投げかけていた。無論この時代、既製服も存在していたが、体にフィットしない不格好で品質の良くない服とされ、通常マネキンに着せることはなかった。したがって一般の人々の眼からは、マネキンが着ている服は高級であり、憧れの対象に見えた。1950年代に入ると世の中も落ち着きを見せ始め、オーダーメードからイージーオーダーへと変化し、百貨店の婦人服売場は、瞬く間にサンプル服を着たマネキンが目立つようになった。
この時代の日本の市場には、海外製マネキンの姿はなく、日本人の美意識や人形観を投影した、日本製のマネキンのみが市場を占有していた。京都の七彩、吉忠、ヤマトの三社に所属していたマネキン作家達は、何れ劣らぬ名作を世に送り続けた。そのうちの一人、村井次郎(1904年〜1982年)は、当時の七彩マネキンの70%を制作し、次々とヒット作を生み出した。村井の婦人マネキンは、日本的な優美さと、時代の先端を生きる新しい女性像を併せ持った、洋装を指向する日本女性の感覚を見事に表現するとともに、日本型マネキンの確立を促した。中でも1953年(昭和28年)伊東絹子がミスユニバース世界3位になった歴史的出来事の直後に制作し、1955年(昭和30年)に発表したFW・117は、日本マネキン史に燦然と輝く村井次郎渾身の名作であり、年間生産体数1650体と言う記録的大ヒットとなった。京都広隆寺の弥勒菩薩を彷佛とさせるこの婦人マネキンは、京人形の伝統に根ざした、日本女性の究極の美しさを表すものであった。これら一連の1950年代のマネキンの素材と製法は、島津マネキン時代同様の楮製紙製で、卓越した京都の職人の手仕事によって作られた。しかし、需要に対し供給が追いつかない
状況が生じ、1959年(昭和34年)、マネキンの素材と製法は、生産性が高く、強くて軽い強化プラスチック(FRP)製に移行したのであった。
マネキンが強化プラスチック製になるまでの九年間、七彩は人形供養ならぬマネキン供養祭を、毎年創業の季節の夏に開催した。それは、戦後の荒み切った世の中にあって、物に対する感謝の念を抱きつつ、人間性を呼び戻したいとの願いのもと、人間と最も密着度の高い間柄にあるマネキン人形の供養を行ない、祭事を通じて人間関係を深めることとした。本社敷地の空地を利用した第1回マネキン供養祭は、1949年(昭和24年)7月、神道、仏教、キリスト教の混合体によって盛大に挙行され、その後、京都の夏の風物詩となった。マネキン供養祭では、マネキンに感謝の気持を奉げると同時に、奇妙奇天烈な仮装とパフォーマンスは、商業活動の道具として人間が作り出し、役割を終えると、この世から姿を消されてしまうマネキンの、モノゆえの儚さを想う人の心を、自らの姿を変えて表現したのであった。
著者: 京都造形芸術大学 ものづくり総合研究センター 主任研究員 藤井秀雪
※この文章は日本人形玩具学会「人形玩具研究 かたち・あそび」第18号 2008 年3月に発表したものの転載です。
| ≪ 戻る | 目次 | 次へ ≫ |