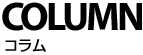
| ≪ 戻る | 目次 | 次へ ≫ |

1920年代のフランス製蝋製マネキン
実際の犬の可愛さに依存して作られた犬型ロボットたちは、いまどこでどうしているのだろうか。当初は、ハイテク技術が生み出したファンタジーに夢中になった人々も、やがて技術の限界が見えてしまうと途端に飽きてしまった。このように、感性やイメージよりも、技術に依存し作られたロボットの運命は哀れだ。しかし、この評価は甚だ主観的かつ性急過ぎるかもしれない。生きている犬同様に、今でも愛の対象として、犬型ロボットと共生している人がいるかも知れない。もし居たとしたら、それは犬型ロボットの能力よりも、その人の想像力と感性に拍手を送るべきだ。ものはいずれ壊れるか、捨てられる哀れな宿命を担っている。悲劇的なのは、まだ壊れてもいないのに、OFF状態のまま、飽きられてしまい、暗い押入れの片隅に押し込まれてしまった犬型ロボットの場合である。押入れから取り出し、壊れてさえいなければ、電源をONにすると、また以前と同じ振る舞いを繰り返す。これはもはや「いきもの」でもペットでもなく、ただの機械としての存在に過ぎない。
一方、本来のいきものの犬の場合はどうだろうか。例えば、道端で雨に濡れながらくんくん鳴いている子犬を拾ってきて飼い始めたとしよう。短い尻尾をふりながら、ころころころがるようにじゃれていた愛らしい頃が過ぎ、とりたててカッコ良さも可愛さもない、平凡この上ないただの犬となっても、ともに過ごした日々が長ければ長いほど、人はその犬に愛着を深め、決してその存在に飽きることはない、それが人と犬との本来的な関係と言えよう。そして決定的なことは、犬の死に直面することだ。人は悲しみ、共に過ごした日々を思い出す。このように人はいきものと共存することが出来る。
さらに人は、ものに対しても、生きているかのような存在感を求めて止まない。現代のロボット開発者は、本来の「いきもの」に少しでも近づけることが、人間とのよりよい関係を実現させることであり、犬型ロボットが、飽きられ見捨てられる悲しい運命に遭遇するのも、ロボットと人間の能力との差異が埋められない技術力にあると考えているようだ。しかし、これは大いなる錯覚である。たとえ本来のいきものに果てしなく近い能力を持った犬型ロボットが開発出来たとしても、人はそのロボットが、機械であることを見抜いた途端、その僅かの差異を識別する能力である感性を働かせるのだ。その差異とは、生きているか、生きていないかの違いであり、生きているとは、決して犬と同じ振る舞いをすることではなく、イメージを投影し続けられる対象であるか否かなのだ。言い換えれば、動くから、発話するから生きているのではなく、静止していても、或いは過去のものであっても、イメージを投影したり、関係し合えるものはすべて「いきもの」であり、前述の「マネキン」が好例であろう。
例えばぬいぐるみの犬を例に考えてみよう。生きている犬のかわいさのイメージを投影してデザインしたのがぬいぐるみだ。もちろん犬型ロボットのような認知能力は持ち合わせていない。そこにあるだけの存在である。したがって、ぬいぐるみの犬は、「好き」「嫌い」「かわいい」「かわいくない」を即座に感性で識別出来る対象なのである。買った当初は溺愛する。こんなかわいいものはこの世にいないと大事にする。しかし、やがてそのぬいぐるみのライバルが現れ、関心の対象から外され、挙句の果ては暗い押入れの中か、棚の上で埃まみれのまま放置される。しかし、そのぬいぐるみを一時的にせよ、受け入れたことがあれば、そこに記憶が残っている。それが捨てられない理由となる。かわいいだけしか存在意味がなく、人に100パーセント委ねて存在するぬいぐるみの犬は、古いマネキン同様に、新たな感性を投影させる対象となり、息を吹き返すのである。このことは、前述した空間演出デザイン学科生のレポートの中に、子供の頃散々遊び、薄汚れたぬいぐるみを押入れの中から探しだし、じっと見つめていると、無性にせつなくてかわいいと思う感情が蘇り、改めて見えるところに飾ったと言う事実が裏付けている。
著者: 京都造形芸術大学 ものづくり総合研究センター 主任研究員 藤井秀雪
※この文章は京都造形芸術大学紀要「GENESIS」第9号に研究ノートとして発表したものの転載です。
| ≪ 戻る | 目次 | 次へ ≫ |